Home|ドラティ(Antal Dorati)|ドヴォルザーク:交響曲第7番 ニ短調, Op.70
ドヴォルザーク:交響曲第7番 ニ短調, Op.70
アンタル・ドラティ指揮 ロンドン交響楽団 1963年7月17日~18日録音
Dvorak:Symphony No.7 In D Minor, Op.70, B.141 [1.Allegro maestoso]
Dvorak:Symphony No.7 In D Minor, Op.70, B.141 [2.Poco adagio]
Dvorak:Symphony No.7 In D Minor, Op.70, B.141 [3.Scherzo: Vivace - Poco meno mosso]
Dvorak:Symphony No.7 In D Minor, Op.70, B.141 [4.Finale: Allegro]
ブラームスの仮面をかぶったシンフォニー
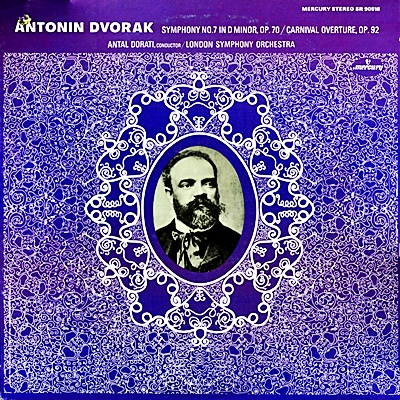
演奏会は空前の大成功をおさめ、ドヴォルザークは協会の名誉会員に選ばれるとともに、協会のために新しい交響曲を書くように依頼されます。
ちょうど同じ頃に、ブラームスの交響曲3番を聞いて深く感動して新たな交響曲の創作に意欲を見せていたドヴォルザークはその依頼を即座に受け入れます。
1884年の2回目のイギリスへの演奏旅行も成功裏に終り、プラハに戻ったドヴォルザークはその年の暮れから創作に取りかかり、翌年の3月には完成させました。その新しい作品が、現在では「第7番」とナンバーリングされている交響曲です。(この交響曲は出版されたときは「第2番」とされていて、それで長らく通用していました。)
この作品は同年4月からの3回目のイギリス訪問で初演され過大にすぎるくらいの成功と評価を勝ち得ました。
一般的、ドヴォルザークとイギリスは相性が良かったようで、イギリスの評論家は常にドヴォルザークの作品に対して高い評価を与えてきました。
その中でも、この作品は特にお気に入りだったようで、シューベルトのハ長調交響曲やブラームスの最後の交響曲に匹敵する傑作とされ続けてきました。(さすがに、今はそんなことを言う人はいないでしょうが・・・)
この作品はドヴォルザークに特有なボヘミア的な憂愁よりは、どこかブラームスを思わせるような重厚さが作品を支配しています。
内省的でどこか内へ内へと沈み込んでいくような雰囲気があります。
ドヴォルザーク自身も出版業者のジムロックにあてて「新しい交響曲に取り組んでもう長期になるが、それは何か本格的なものになりそうだ」と述べています。
その「本格的なもの」とはブラームスの交響曲をさしていることは明らかです。
誤解を招くかもしれませんが、ドヴォルザークがブラームスの仮面をつけて書いたような音楽です。
伝説の名録音~マーキュリー・レーベル
今もマーキュリーレーベルの録音は伝説です。彼らのキャッチフレーズだった「You are there」は、決して誇大広告ではありません。
その録音の特徴は、とびきりの鮮明さと空間いっぱいに広がるダイナミックな響きの見事さにあると言えます。そして、この伝説の録音を実現したのが、録音史上最も耳の良いプロデューサーと言われたウィルマ・コザードでした。
彼女は、モノラルならば一本のマイク、ステレオ録音になってからは左右に一本ずつ追加して合計で3本というスタイルを厳格に守り続けました。いわゆるワンポイント録音という手法ですが、これでは3トラックに録音した音を2チャンネルにトラックダウンするだけですから、録音してからの調整などはほとんどできません。
適当なセッティングでも、後からいくらでも調整が可能なマルチマイク録音とは、思想が根本から違うのです。
ベストのマイクセッティングを得るためには天才的な閃きが求められます。
さらに言えば、この録音手法は演奏する側にも多大なるプレッシャーを与えます。
録音してからいかようにも料理できるマルチマイク録音と違って、ワンポイント録音の場合は演奏する側にも一切の誤魔化しを許さないからです。その意味でも、この録音で確認できるオケのクオリティには一切の誤魔化しはないのです。
さらに、コザートは厳格なワンポイント録音にこだわるだけでなく、使用するマイクにはテレフンケンの最高級のものを使い、さらには映像用の35ミリフィルムに特殊な磁気層を塗布した録音テープを使う特製の録音デッキまで用意するという徹底ぶりでした。
そして、そこまでして丁寧にすくい上げた録音データは、当然のようにいかなるリミッターやコンプレッサー、さらにフィルターなども一切使わずにそのままカッティングされました。
「初期のワンポイント録音は、その場の空気感をとらえてあまり音圧を上げずDレンジを広いまま入れるような音作りでした。・・・それらは超高級オーディオで聞けば最高にいい音でもあっても、一般リスナーには・・・迫力不足になりかねないのも事実でした。ですから、現在はどちらのユーザーにも満足してもらえるように・・・両立を心がけています。」なんてことを恥ずかしげもなく語る現在の録音エンジニアに聞かせてやりたいほどの(まあ、知ってはいるでしょうが・・・^^;)徹底ぶりなのです。
このシンプルさへの徹底が、異次元とも言えるような鮮明さととんでもないダイナミックさを実現したのです。
しかし、そんなマーキュリーレーベルも60年代に入って大手フィリップスの傘下にはいると、コザートのような採算度外視の徹底ぶりは経営陣に嫌われて追い出される羽目になります。彼女が去ってからもマーキュリーの名前は残ったのですが、その内実は「伝説」と言われたレーベルのものとは全く別物になってしまいました。
いつの時代も大手というのはつまらん存在です。
しかし、コザートが実現した異次元レベルの鮮明さは顕微鏡で毛穴の奥までのぞき込むようなものでした。ですから、その録音はオケのちょっとした荒さであっても、その荒さを白日の下にさらけ出してしまいます。
これが、実に辛いところなのです。
ドラティの録音で言えば、彼女が1949年から1960年まで音楽監督を務め、オーケストラビルダーとして鍛え上げていたミネアポリス交響楽団であっても、このコザートの録音だと荒さがどうしても耳についてしまうのです。言葉をかえれば、コザートはそのような部分についても、分かっていながらも一切の容赦も手抜きもしなかったのです。
ところが、オケがロンドン交響楽団なんかだと事情は全く変わってしまうのです。少し前に紹介したドヴォルザークのスラブ舞曲集(1958年4月録音 ミネアポリス交響楽団)では感じた荒さが、ほぼ同時期の録音である交響曲第8番(1959年 ロンドン交響楽団)や7番(1963年 ロンドン交響楽団)ではそれほど強く感じないのです。
そのことは、同じくロンドン交響楽団と録音したチャイコフスキーの4番(1960年)や6番(1960年)、ベートーベンの5番(1962年)、6番(1962年)、7番(1963年)などにも言えます。
くるみ割り人形(1962年7月)の時にも感じたのですが、この時期のロンドン交響楽団というのはただ者ではありません。一部では、すでに落ち目になり始めていたという批評もあるのですが、この録音を聞いて落ち目と思うならばほとんどのオケはゴミ同然です。
ただし、録音的に面白いなと思うのは、そう言う荒さが、「You are there」というレーベルのキャッチフレーズを生々しく思い起こさせるという事実です。それは上手な化粧で欠点を覆い隠した偽物の美女よりはよほど美しいのです。
そして、そのことは、さすがのロンドン交響楽団をもってしても部分的には当てはまるのです。
半世紀も前に、録音という芸術がすでにこのレベルにまで達していたことは心に留めておくべきでしょう。変化は必ずしも進歩ではありませんし、時が経れば物事は前へ進むものだと考えるのは愚か者だけです。
この演奏を評価してください。
- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2
- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4
- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6
- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8
- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10
- 件名は変更しないでください。
- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。
よせられたコメント
【リスニングルームの更新履歴】
【最近の更新(10件)】
[2026-02-08]
ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)
[2026-02-06]
ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)
[2026-02-02]
ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)
[2026-01-31]
ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)
[2026-01-27]
ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)
[2026-01-25]
J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)
[2026-01-21]
ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)
[2026-01-19]
フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)
[2026-01-16]
ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)
[2026-01-14]
マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)








