Home| 作曲家で選ぶ | MAHLER
幼くして音楽的才能を発揮したため、父は息子の才能に期待をかけて6歳からピアノを学ばせる。1869年から高等学校に在学し、75年からはウィーンにおもむいて音楽を専門的に学びはじめる。
また、大学でブルックナーの音楽論の講義を聴講して感銘を受け親しく交際を始めるとともに、フーゴー・ヴォルフとも親交を深める。
1888年にはブダペスト王立歌劇場の正指揮者に就任し、その後ハンブルグの歌劇場を経て、1897年からはウィーン宮廷歌劇場の指揮者へとキャリアを積み上げていく。
このような指揮活動の間に作曲活動を行い、第1交響曲、第2交響曲などが初演されるようになって作曲家マーラーとしても認められるようになっていく。
しかし、1898年からはウィーンフィルの指揮も行うようになってその演奏活動は多忙を極め、作曲活動はオフシーズンの夏に行われるようになっていく。このような生活が1900年から1907年まで続き、この間に第5から第7までの交響曲が生み出される。
1907年には劇場との不和が頂点に達してウィーンを去り、また今後作曲活動に専念する経済的基盤を築くために、有利な条件を提示されたニューヨークに向かう。
ニューヨークでは冬のシーズンは演奏活動に専念し、夏は作曲活動に専念するという生活をおくり、第8、大地の歌・第9交響曲を完成させる。
しかし、1910年には心臓発作が激しくなったため、医師の進めで4月にはヨーロッパに帰国してパリで静養につとめる。しかし、治療の甲斐もなくウィーンに移って5月18日になくなる。
昔はクラシック音楽にふれる第一歩はモーツァルトかベートーベン、ピアノをやる人はバッハかショパンあたりと相場が決まっていたものです。
マーラーなんてのはよほどのマニア(?)でもない限り聞かなかったものです。
ところが最近は少し下火になったようですが、一時は大変なマーラーブームで、はじめて聴いたクラシック音楽がマーラーの9番(!)なんて言う大変な人も現れてきました。
「とにかくなんだか訳の分からない人!」というのが長年のマーラー評価でした。
映画「ヴェニスに死す」で描かれた音楽家はマーラーがモデルだといわれていますが、あの醜悪きわまる音楽家のイメージがそのまま当時のマーラーのイメージでもありました。おそらくマーラーを愛する多くの善良なクラシック音楽ファンは、あの映画を見れば怒りで身が震えることを100%保証できます。(^^)
それが、今やベートーベンやブラームスと肩を並べるコンサートの定番プログラムになったのですから、時代も変われば変わるものです。
その複雑で巨大な音楽ゆえになかなか理解されなかったマーラーですが、それでも彼は「いつか私の時代が来る!」と言い続けていました。
そして、彼は生前このようにも語っていました。
「私は三重の意味で異邦人だった。チェコではボヘミア人、ドイツではオーストリア人、そして世界の中ではユダヤ人だった。私は成功を得るためにはどこへでも顔をつっこんでいった。そしてどこでも歓迎されなかった。」
「私の時代」を引き寄せるというのも大変なことです。
MAHLER
<ボヘミア:1860〜1911>
経歴
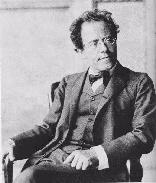
幼くして音楽的才能を発揮したため、父は息子の才能に期待をかけて6歳からピアノを学ばせる。1869年から高等学校に在学し、75年からはウィーンにおもむいて音楽を専門的に学びはじめる。
また、大学でブルックナーの音楽論の講義を聴講して感銘を受け親しく交際を始めるとともに、フーゴー・ヴォルフとも親交を深める。
1888年にはブダペスト王立歌劇場の正指揮者に就任し、その後ハンブルグの歌劇場を経て、1897年からはウィーン宮廷歌劇場の指揮者へとキャリアを積み上げていく。
このような指揮活動の間に作曲活動を行い、第1交響曲、第2交響曲などが初演されるようになって作曲家マーラーとしても認められるようになっていく。
しかし、1898年からはウィーンフィルの指揮も行うようになってその演奏活動は多忙を極め、作曲活動はオフシーズンの夏に行われるようになっていく。このような生活が1900年から1907年まで続き、この間に第5から第7までの交響曲が生み出される。
1907年には劇場との不和が頂点に達してウィーンを去り、また今後作曲活動に専念する経済的基盤を築くために、有利な条件を提示されたニューヨークに向かう。
ニューヨークでは冬のシーズンは演奏活動に専念し、夏は作曲活動に専念するという生活をおくり、第8、大地の歌・第9交響曲を完成させる。
しかし、1910年には心臓発作が激しくなったため、医師の進めで4月にはヨーロッパに帰国してパリで静養につとめる。しかし、治療の甲斐もなくウィーンに移って5月18日になくなる。
ユング君の一言
昔はクラシック音楽にふれる第一歩はモーツァルトかベートーベン、ピアノをやる人はバッハかショパンあたりと相場が決まっていたものです。
マーラーなんてのはよほどのマニア(?)でもない限り聞かなかったものです。
ところが最近は少し下火になったようですが、一時は大変なマーラーブームで、はじめて聴いたクラシック音楽がマーラーの9番(!)なんて言う大変な人も現れてきました。
「とにかくなんだか訳の分からない人!」というのが長年のマーラー評価でした。
映画「ヴェニスに死す」で描かれた音楽家はマーラーがモデルだといわれていますが、あの醜悪きわまる音楽家のイメージがそのまま当時のマーラーのイメージでもありました。おそらくマーラーを愛する多くの善良なクラシック音楽ファンは、あの映画を見れば怒りで身が震えることを100%保証できます。(^^)
それが、今やベートーベンやブラームスと肩を並べるコンサートの定番プログラムになったのですから、時代も変われば変わるものです。
その複雑で巨大な音楽ゆえになかなか理解されなかったマーラーですが、それでも彼は「いつか私の時代が来る!」と言い続けていました。
そして、彼は生前このようにも語っていました。
「私は三重の意味で異邦人だった。チェコではボヘミア人、ドイツではオーストリア人、そして世界の中ではユダヤ人だった。私は成功を得るためにはどこへでも顔をつっこんでいった。そしてどこでも歓迎されなかった。」
「私の時代」を引き寄せるというのも大変なことです。
【リスニングルームの更新履歴】
【最近の更新(10件)】
[2026-02-12]
シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)
[2026-02-10]
フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)
[2026-02-08]
ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)
[2026-02-06]
ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)
[2026-02-02]
ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)
[2026-01-31]
ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)
[2026-01-27]
ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)
[2026-01-25]
J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)
[2026-01-21]
ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)
[2026-01-19]
フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)








