クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~
ベートーベン:交響曲第6番ヘ長調, Op.68「田園」
ヤッシャ・ホーレンシュタイン指揮 ウィーン・プロ・ムジカ管弦楽団 1958年録音
Beethoven:Symphony No.6 in F major , Op.68 "Pastoral" [1.Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande.Allegro ma non troppo]
Beethoven:Symphony No.6 in F major , Op.68 "Pastoral" [2.Scene am Bach. Andante molto moto]
Beethoven:Symphony No.6 in F major , Op.68 "Pastoral" [3.Lustiges Zusammensein der Landleute. Allegro]
Beethoven:Symphony No.6 in F major , Op.68 "Pastoral" [4.Gewitter. Sturm. Allegro]
Beethoven:Symphony No.6 in F major , Op.68 "Pastoral" [5.Hirtengesang. Frohe und dankbare Gefuhle nach dem Sturm. Allegretto]
標題付きの交響曲
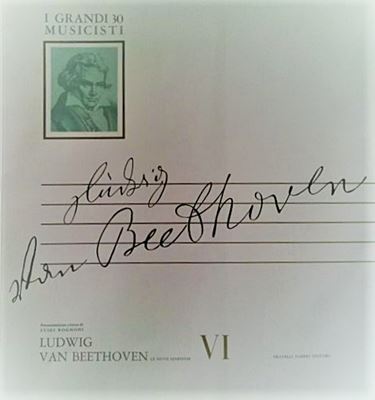
- 第1楽章:「田園に到着したときの朗らかな感情の目覚め」
- 第2楽章:「小川のほとりの情景」
- 第3楽章:「農民の楽しい集い」
- 第4楽章:「雷雨、雨」
- 第5楽章:「牧人の歌、嵐のあとの喜ばしい感謝の感情」
また、第3楽章以降は切れ目なしに演奏されるのも今までない趣向です。
これらの特徴は、このあとのロマン派の時代に引き継がれ大きな影響を与えることになります。
しかし、世間にはベートーベンの音楽をこのような標題で理解するのが我慢できない人が多くて、「そのような標題にとらわれることなく純粋に絶対的な音楽として理解するべきだ!」と宣っています。
このような人は何の論証も抜きに標題音楽は絶対音楽に劣る存在と思っているらしくて、偉大にして神聖なるベートーベンの音楽がレベルの低い「標題音楽」として理解されることが我慢できないようです。ご苦労さんな事です。
しかし、そういう頭でっかちな聴き方をしない普通の聞き手なら、ベートーベンが与えた標題が音楽の雰囲気を実にうまく表現していることに気づくはずです。
前作の5番で人間の内面的世界の劇的な葛藤を描いたベートーベンは、自然という外的世界を描いても一流であったと言うことです。同時期に全く正反対と思えるような作品を創作したのがベートーベンの特長であることはよく知られていますが、ここでもその特徴が発揮されたと言うことでしょう。
またあまり知られていないことですが、残されたスケッチから最終楽章に合唱を導入しようとしたことが指摘されています。
もしそれが実現していたならば、第五の「運命」との対比はよりはっきりした物になったでしょうし、年末がくれば第九ばかり聞かされると言う「苦行(^^;」を味わうこともなかったでしょう。
ちょっと残念なことです。
指揮棒一本を手にした渡り職人
ヤッシャ・ホーレンシュタインと言う名前も今ではかなり忘却の彼方に沈みつつあります。第2次大戦は多くの音楽家に苦難をもたらしたのですが、このホーレンシュタインもその典型のような音楽家人生を強いられました。
ホーレンシュタインはフルトヴェングラーの助手として修行を重ね、若くしてデュッセルドルフ・オペラの音楽総監督に就任するなど順調にキャリアの第一歩を踏み出しています。しかし、1933年にナチスが政権するとユダヤ人だった彼の境遇は一変し、結局はアメリカへの亡命を余儀なくされます。
そして、不思議なのは、戦争が終わってヨーロッパの楽団に復帰するものの最後まで特定の楽団のシェフというポストを得られなかったことです。
もちろん、能力がなければそれも仕方のない話なのですが、残された録音を聞けば分かるように指揮者としての能力は半端ではないことがよく分かります。とりわけ、ブルックナーやマーラーを得意としたことからも分かるように、大規模な編成のオケを完璧にコントロールする能力は抜きんでていたと言われます。(伝聞系の物井なのは彼のマーラーやブルックナーを聞いたのははるか昔のことなので余り記憶がさだかでないからです。^^:)
それ故に、客演指揮だけでその指揮者人生を終わったのですが、どんなオーケストラに招かれてもそれなりの音楽に仕上げてしまうと言う凄技を持っていました。
それは例えてみれば、道具一式を担いで、己の腕一本で各地を渡り歩く「渡り職人」を彷彿とさせます。
つまりは指揮棒一本を手にしてどんなオーケストラに招かれても、そして、その能力に少なくない問題を抱えているオーケストラであっても、コンサート当日までにはそれなりのレベルに上げてしまう職人指揮者だったのです。
それだけに、それほどの能力を持ちながら生涯特定のポストを手に入れることが出来なかったというのは実に不思議な話です。
それとも、そう言う特定のポストにつきまとうあれこれの煩わしい業務をホーレンシュタイン自身が嫌ったのでしょうか。
それにしても、ここで紹介している50年代に録音されたベートーベンを聞くと、あれこれと複雑な思いをかき立てられずにはおれません。
ここで彼が指揮している「ウィーン・プロ・ムジカ管弦楽団」というのは実に怪しげな楽団名であり、渡り職人には「相応しい^^;」オケのように思えます。しかし、この楽団は怪しいオケ等ではなくて、その実態は「ウィーン交響楽団」でした。
では、どうして「ウィーン交響楽団」ではなくて「ウィーン・プロ・ムジカ管弦楽団」とクレジットされたのかと言えば、それは当時の音楽監督だったカラヤンの強い意向によるものでした。つまりは、ウィーン交響楽団はカラヤンが指揮したときにだけ正式な名称を名乗る事が許され、それ以外の指揮者が録音をするときには「ウィーン交響楽団」の名称を使うことをカラヤンが強く禁じたのです。
カラヤンという指揮者は疑いもなく優れた指揮者であったことは認めざるを得ません。しかし、同時に、自分の敵になりそうな人物にはあれこれの政治的手段を使って芽のうちにつみ取ると言うことにも熱心な人物でした。
バーンスタインがベルリン・フィルの指揮台に立てたのは一度しかなかったというのは有名な話です。
そして、このホーレンシュタインと「ウィーン・プロ・ムジカ管弦楽団」との演奏を聞けば、もしも彼がこのオケのシェフとして活躍することが出来ればどれほど素晴らしい成果が残せた事だろうと思わざるを得ません。
低声部をドッシリと鳴らしたヨーロッパの伝統的な響きをウィーン響からひきだしているのは実に見事なのです。このあたり、フルトヴェングラーのもとで修行したという音楽的なルーツを感じてしまいます。
そして、そう言う響きはカラヤンの棒からは引き出せないものでもありました。もっとも、カラヤンにはそのような響きは時代遅れのもので、そんな響きを出す気もなかったでしょうが、それでもおそらくは「出せなかった」のではないかと思われます。
しかしながら、どうしても客演という限界があるのか、もう一歩踏み込むことが出来ずに、最後は手際よくまとめている部分が垣間見られて実に残念です。例えば、ここで紹介している田園では随分と大人しい嵐の場面におさえています。
もっとも、その手際よくまとめたレベルは決して低いものではないので、客演一本でよくぞこれほどの世界を築き上げていったものだとは思います。
いや、考えてみればベートーベンの交響曲を「手際よくまとめる」などと言うことは絶対に不可能です。
あれは、演奏者に対して常にあらん限りの献身と熱量を要求する音楽です。「もう一歩踏み込むことが出来ずに、最後は手際よくまとめている」などと言うのは聞き手の勝手な戯言であり、そうではなくて、そこにどれほど困難な条件があっても、その中でベストをつくした姿を見るべきなのでしょう。
ただし、彼の本領が発揮されているのはマーラーやブルックナーです。しかしながら、年を重ねてくると、なかなかそう言う音楽を聞くというのはきつくなってきます。(^^;ある方から「安心して聞けるベートーベン」というコメントをいただきましたが、年を重ねてくるとなかなかに含蓄のある言葉だと思いました。
とは言え、いつかは聞かざるを得ないなという思いにはさせてくれたベートーベン演奏でした。
よせられたコメント
2021-12-04:joshua
- プロムジカ、こと「隠れ」ウィーン響の音がいいですね。楽員が指揮者に共感して伸び伸び音を紡いでる、そんな好ましい演奏風景が感じられます。ヤッシャ・ハイフェッツならぬ、ヤッシャ・ホーレンシュタインさん。好かれる客演指揮者って、多国を旅してまわる大道芸人みたいなものですかね?本人が楽しめたら、楽員が嫌がらなかったら、それでいいと思います。
【リスニングルームの更新履歴】
【最近の更新(10件)】
[2026-01-14]
マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)
[2026-01-12]
シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)
[2026-01-10]
バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)
[2026-01-07]
ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)
[2026-01-05]
ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)
[2026-01-03]
フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)
[2025-12-31]
ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)
[2025-12-29]
ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)
[2025-12-26]
ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)
[2025-12-24]
フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)








