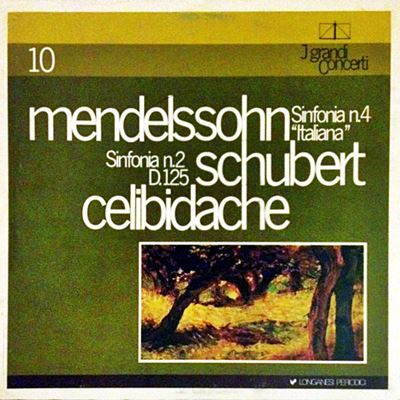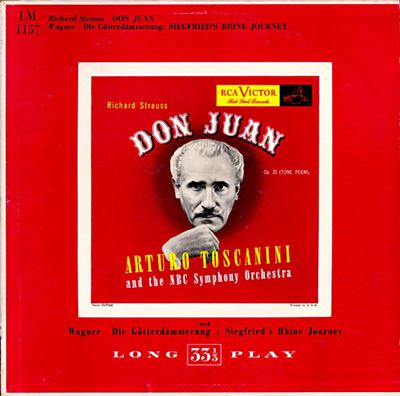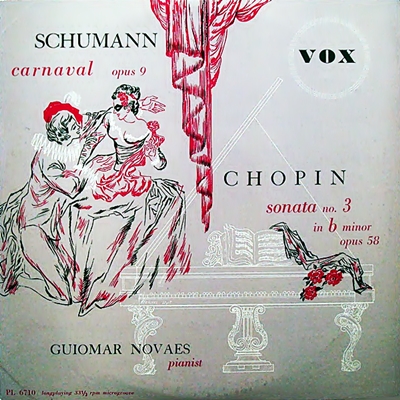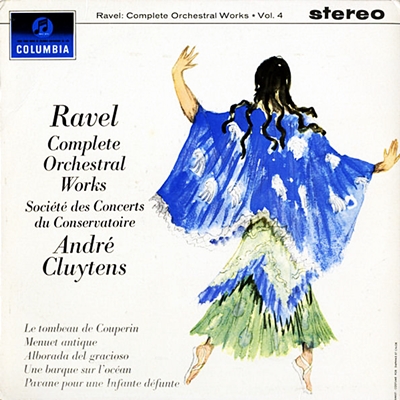Home|Blue Sky Label~更新履歴
作曲家で選ぶ
演奏家で選ぶ
[2023-07-07]・・・モーツァルト:オーボエ四重奏曲 ヘ長調, K.370(Mozart:Oboe Quartet in F major, K.370/368b)
(Ob)ピエール・ピエルロ:パスキエ・トリオ 1950年代録音(Pierre Pierlot:Pasquier Trio Recorded on 1950s)パスキエ・トリオはその名の通りパスキエ3兄弟によって1927年に結成された室内楽団です。彼らは父親はヴァイオリニスト、母親はピアニストという音楽家の家庭で育ち、長男のピエール・パスキエがヴィオラ、次男のジャン・パスキエがヴァイオリン、三男の...
[2023-07-06]・・・メンデルスゾーン:交響曲第4番 イ長調 作品90 「イタリア」(Mendelssohn:Symphony No.4 in A major, Op.90 "Italian")
セルジュ・チェリビダッケ指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1950年1月20日録音(Sergiu Celibidache:the Berlin Philharmonic Orchestra Recorded on January 20, 1950)敗戦直後の瓦礫の街と化したベルリンで演奏されたブラームスの4番を聞いたときは驚きのあまり仰け反ってしまいました。おそらく、私がこういう歴史的録音を紹介しようと思い立った要因の一つであったことは間違いありません。 あのチェリビダッケとベルリ...
[2023-07-05]・・・モーツァルト:ピアノ三重奏曲第1番 変ロ長調, K.254(Mozart:Divertimento in B-flat major, K.254)
(P)パウル・バドゥラ=スコダ (Cello)アントニオ・ヤニグロ (Violine)ジャン・フルニエ 1956年発行(Antonio Janigro:(P)Paul Badura-Skoda (Violine)Jean Fournier Released on 1956)ピアノ・トリオと言うものはなかなか難しいものです。パスキエ・トリオみたいな弦楽トリオよりは作品のレパートリーは多いのでしょうが、それでも常設で活動するとなるとなかなか難しいものがあるようです。 ボザール・トリオの様な存在は珍しくて、古いとこ...
[2023-07-04]・・・ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調, Op.26(Bruch:Violin Concerto No.1 in G minor, Op.26)
(Vn)ミッシェル・オークレール:ヴィルヘルム・ロイブナー指揮 オーストリア交響楽団 1952年1月26日~27日録音(Michele Auclair:(Con)Wilhelm Loibner Austrian Symphony Orchestra Recorded on 1952)オークレールはパリ音楽院のブシューリのもとで学んだのですが、同門のヴァイオリニストとしてはジネット・ヌボーとローラ・ボベスコ等がいます。その後、1943年にロン=ティボー音楽コンクールで第一位を獲得してジャック・ティボーの知遇を得ます。ただ...
[2023-07-03]・・・コダーイ:「ハーリ・ヤーノシュ」 組曲, Op.35a(Kodaly:Hary Janos suite, Op.35a)
ディミトリ・ミトロプーロス指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック 1956年2月27日録音(Dimitris Mitropoulos:New York Philharmonic Recorded on February 27, 1956)昨今は右を見ても左を見てもAI絡みの話題があふれています。 すでに、AIの進歩は勝ち負けがはっきりするゲームにおいては人間の領域をはるかに凌駕してしまいました。さらに、生成AIは文章や画像などをまるで人間が作ったかのように作り出します。 ...
[2023-07-02]・・・R.シュトラウス:交響詩「ドンファン」, Op.20(Richard Strauss:Don Juan, Op.20)
Arturo Toscanini:NBC Symphony Orchestra Recorded on January 10, 1951(アルトゥーロ・トスカニーニ指揮 NBC交響楽団 1951年1月10日録音)ふと気づいてみれば、トスカニーニがリヒャルト.シュトラウスの作品を録音しているではないですか。 最初は「ふーん」というくらいだったのですが、聞いてみればこれが実に素晴らしい演奏なので驚いてしまいました。とりわけ、「ティル・オイレンシュピー...
[2023-07-01]・・・ワーグナー:「タンホイザー」よりバッカナール(Wagner:Bacchanale from "Tannhauser")
ヤッシャ・ホーレンシュタイン指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 ビーチャム合唱連盟 1962年9月録音(Jascha Horenstein:Royal Philharmonic Orchestra Beecham Choral Society Recorded on September 1962)ホーレンシュタインという指揮者は本当に謎としか言いようがありません。戦前はフルトヴェングラーの助手も務め順調にキャリアを積み上げていったのですが、ナチスの台頭でアメリカに亡命を余儀なくされ、戦後は1949年にヨーロッパに復帰するものの特定の...
[2023-06-30]・・・ヘンデル:オンブラ・マイ・フ(Handel:Ombra mai fu)
(Cello)パブロ・カザルス:1915年1月15日録音(Pablo Casals:Recorded on January 15, 1915)大阪狭山市でアナログレコードを聞き合う集まりが毎月開催されています。毎月、顔なじみとあれこれおしゃべりできる時間は本当に貴重です。もちろん、持ち寄ったアナログ・レコードを聞くのも楽しみですが・・・(^^; その集まりで少し前の話なのですが...
[2023-06-29]・・・ショパン:ピアノ・ソナタ第3番 ロ短調, Op.58(Chopin:Piano Sonata No.3 in B minor, Op.58)
(P)ギオマール・ノヴァエス:1951年発行(Guiomar Novaes:Published in 1951)ギオマール・ノヴァエスはかなりまとまった数のショパン作品を録音しています。この時代を考えれば(今の時代も同じかも)当然と言えば当然なのかもしれませんが、やはり聞き手にとっては嬉しい事実です。 ノヴァエスは「ブラジルの偉大なピアニスト」...
[2023-06-28]・・・ラヴェル:道化師の朝の歌(Ravel:Alborada del gracioso)
アンドレ・クリュイタンス指揮 パリ音楽院管弦楽団 1962年10月録音(Andre Cluytens:Orchestre de la Societe des Concerts du Conservatoire Recorded on October, 1962)「モノラルでも録音していたんだ」と最近になって気づいて大いに興味をそそられたと書きながら、肝心のステレオ録音の方の紹介が中途半端になっていることに気づきました。 「マ・メール・ロワ」に「ダフニスとクロエ」、そして、「高雅にして感傷的なワル...