クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~
モーツァルト:音楽の冗談, K.522
ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団:(Hr)ハンス・ベルガー&Josef Koller (Contrabasss)ヨーゼフ・ハーマン 1954年録音
Mozart:Ein musikalischer Spass, K.522 [1.Allegro]
Mozart:Ein musikalischer Spass, K.522 [2.Menuett: Maestoso]
Mozart:Ein musikalischer Spass, K.522 [3.Adagio cantabile]
Mozart:Ein musikalischer Spass, K.522 [4.Presto]
神は常に不平等であり、不条理
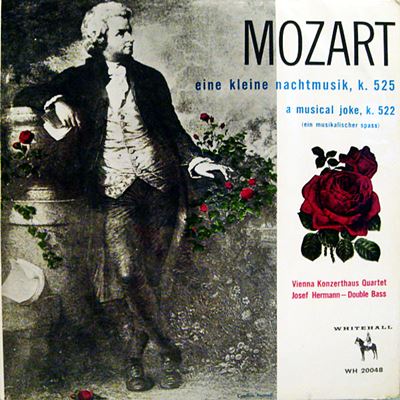
そんな一年は笑って送り出すしかないでしょう。Good by 2021!
この作品は、長く、父であるレオポルドの死と、さらには3年間も可愛がっていたムクドリの死の後に書かれたと考えられていて、それらの喪失とこの音楽との間に存在するあまりにも大きな乖離は多くの研究者を悩ませてきました。多くの研究者はその「謎」を解くために様々な精神分析学的なアプローチを行ったのですが、最近になってその「謎」は容易に解けることになりました。
分かってみれば実に簡単な話であって、父の死を知った後に書かれたと思われていたこの「音楽の冗談」は、実はそれ以前にほぼ書かれていたことが判明したのです。つまりは、父の死やムクドリの死はこの作品とはなんの関係もなかったのです。
映画「アマデウス」で、多くの仲間の前でふざけてピアノを演奏し、さらには「これはサリエリ風」などといって彼らの音楽の程度の低さをからかう場面がありました。実は、あのような集まりは当時のウィーンでは頻繁に行われていたようで、不出来な作品を徹底的にパロディ化をしていたのです。
それにしても、この「音楽の冗談」は天才から見た能なしどもの音楽がどの様に見えるのかを如実にあらわしています。
まちがっても、その混乱と音程の外れ方、脈絡のない熱狂の不自然さなどは演奏者の未熟さ故ではありません。それらは全てモーツァルトの楽譜に書かれたままに演奏をしているのです。
そう言えば、NHKの朝ドラ「あまちゃん」で鈴鹿ひろ美(薬師丸ひろ子)が実際に歌う「潮騒のメモリー」を聞かされた主人公(能年玲奈 )が「こんな歌なんですか」と聞き返すと、マネージャーの水口琢磨(松田龍平)が「もしも、楽譜通りに歌ってこんな歌だったら超絶技巧だよ」とこたえるような場面がありました。
まさに、この作品を演奏するにはその様な「超絶技巧」が求められる作品です。
それにしても、サリエリではありませんが、神は常に不平等であり、不条理な存在です。、
違うからこそいい
ウィーンフィルにはコンサートマスターを中心に各パートの首席がカルテットを結成する習慣があります。しかし、このコンツェルトハウス四重奏団はその様な楽団ではなくて、首席奏者の後ろで演奏しているメンバーたちが自主的に結成したものです。
ちなみに、この時代のエリート四重奏団はワルター・バリリをリーダーとしたバリリ四重奏団でした。
まあ、言ってみればバリリ四重奏団の方はウィーン・フィルという「金看板」を背負わざるをえないのですが、コンツェルトハウス四重奏団のほうにはそう言うプレッシャーがありません。ですから、彼らの演奏はいつも親密で寛いだ雰囲気がただよっていて、カルテットというスタイルに伴う緊張感のようなものとは無縁です。
そう言えば、以前にもふれたのですが、この四重奏団のリーダーだったカンパーのことを「彼はムジカー(音楽家)だったが、同時にムジカント(楽士)でもあった」と評した人がいました。
それは、優れた芸儒的な資質は持っているものの、心の奥には街の辻で音楽を楽しげに演奏するような心を失う事はなかったという誉め言葉でしょう。
それ故に、彼らの演奏するハイドンやベートーベン、そしてモーツァルトなどには「我らが町の音楽」という強い自負に裏打ちされた自由さが溢れています。そして、その様な自由さに裏打ちされた音楽は、機能美に溢れたハイテク・カルテットが生み出す音楽とは随分と雰囲気が異なるのですが、まさにそこにこそ彼らの値打ちがあります。
そして、独奏者を務めているオーボエのハンス・カメシュもフルートのハンス・レズニチェックもともにウィーン・フィルの仲間であり、その価値観は共有されています。
音楽の冗談で一緒に演奏しているメンバーもおそらくは全てウィーンフィルのメンバーでしょう。そうでなければ、これほどまでに楽しく演奏が出来るはずがありません。
いつも言っていることですが、今の時代には聞くことのできない演奏を聞けるというのは古い録音を巡り歩く楽しみです。
そしt、それが普通の演奏とはスタイルからあまりにも異なるからと言って拒否するならば、それは人生の楽しみの少なくない部分を失うことを意味していまか。
言葉をかえれば、違うからこそいいのです。
よせられたコメント
2022-01-01:コタロー
- 新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
モーツァルトの「音楽の冗談」、曲名だけは知っていたのですが、今まで聴くチャンスがなく、この曲のファーストコンタクトです。ありがとうございました。
実際に聴いてみると、「軽い冗談」という感じで、我々のような現代人からみると奇矯さはさほど感じませんでした。むしろウィーン・コンツェルトハウス四重奏団の手にかかると、優雅な感じが前面に出ています・・・と思って聴いていたところ、終楽章の最後に登場する不協和音はなかなかに強烈ですね。
この曲は、ガチのクラシック音楽ファンにぜひ聴かせたいところですね。
【リスニングルームの更新履歴】
【最近の更新(10件)】
[2026-02-22]
ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)
[2026-02-18]
ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)
[2026-02-16]
スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)
[2026-02-12]
シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)
[2026-02-10]
フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)
[2026-02-08]
ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)
[2026-02-06]
ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)
[2026-02-02]
ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)
[2026-01-31]
ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)
[2026-01-27]
ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)









